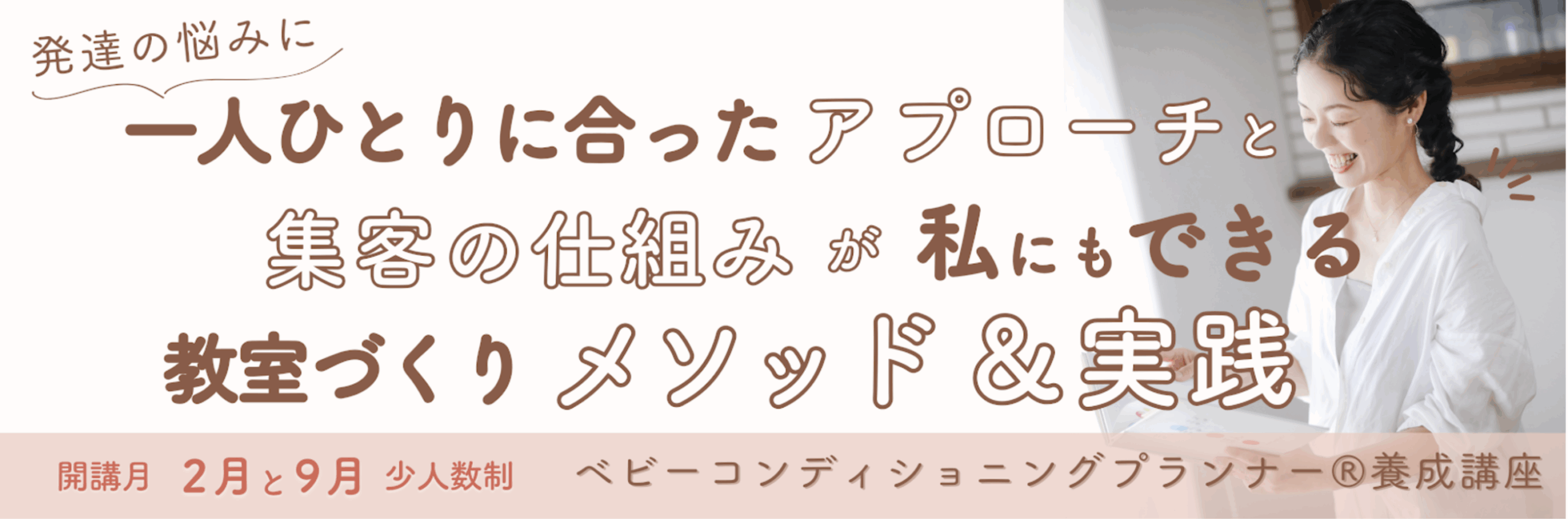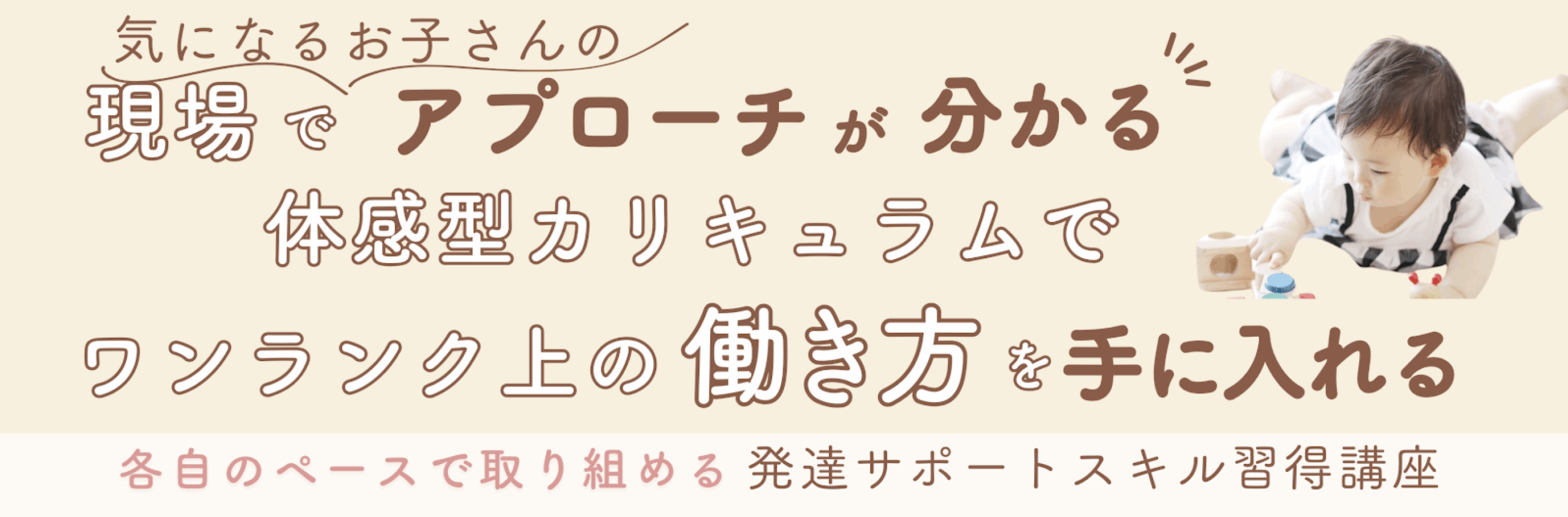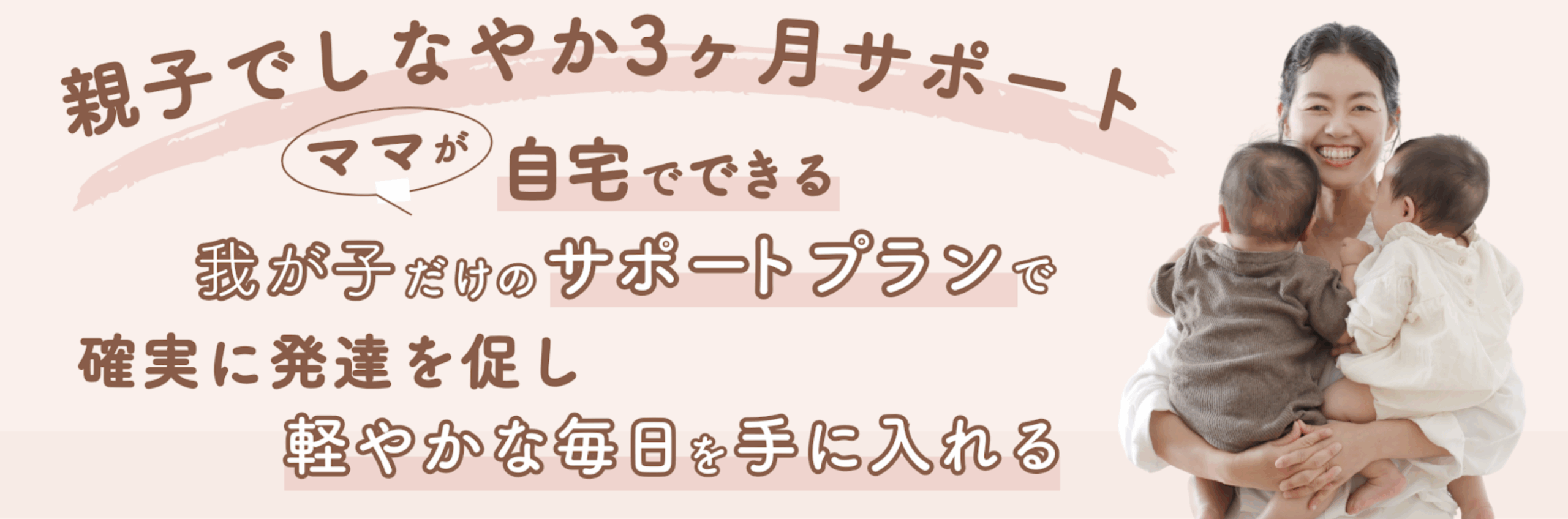6ヶ月で寝返りしない…実はよくある悩みです
「上の子は6ヶ月で寝返りしてハイハイもしていたのに…」
同じ月齢でも、兄弟でこんなに違うの?と不安になること、ありますよね。
でも実は、6ヶ月で寝返りができない赤ちゃんは珍しくありません。
育児本や周りの情報にとらわれすぎず、「今その子にとって必要な経験は何か?」という視点がとても大切なんです。
今回ご相談いただいたママも、
- 仰向けは好きだけどうつ伏せになるとすぐ泣く
- 反るような動きが多くて、寝返りしそうでしない
- 一時期だけ寝返り返りをしたが最近はしない
といったお悩みを抱えていました。
これらの姿勢や動き方は、赤ちゃんの身体からの“サイン”でもあります。
まずは“今の姿勢”と“動き方”を観察するところから
赤ちゃんが今どんな姿勢でリラックスしているか、どの動きで戸惑っているか。
「できる・できない」ではなく、「どんな姿勢・動きが得意で、苦手なのか?」を観察することで、サポートの方向性が見えてきます。
たとえば今回の赤ちゃんは、仰向けでは笑顔でよく動くけれど、うつ伏せになると力が入りすぎて反ってしまう。
これも、「背中側が張りやすくて、前面の使い方がまだうまくいっていない」というヒントになりました。
寝返りのステップには、左右バランス・重心移動・軸の感覚などが関係しています。
首や肩、腰の動きに左右差がないか、向きぐせがあるかなども、丁寧に見ていくことで関わり方が変わります。
日常でできる!赤ちゃんの動きを引き出すサポート
力が入りやすい赤ちゃんには、背中や肩甲骨まわりのマッサージで緊張をゆるめるのが効果的です。
ふれるときは「抱っこの時」や「うつ伏せで遊んでいる時」など、ママが日常の中でどのタイミングで触れる事ができそうか一緒に決めていきます。
寝る姿勢や、いつもの抱っこの重心を観察してみて下さい。片方の重心に偏りが見られるようなら、経験値の少ない重心方向も、「抱っこでゆっくりお歌に合わせて揺れる」「バスタオルなどで重心を傾けて遊ぶ」など楽しみながら重心遊びを行います。
すると、重心経験が豊富になり、赤ちゃんの動きが変わってくることがあります。また、向き癖はマッサージで筋肉からケアすると改善しやすいです。
おもちゃの位置を工夫して、追視遊びから「手をのばしたくなる」「横向きになる」ような環境づくりもおすすめです。目の動き・手の動きを引き出すには、「追視遊び」「握る遊び」から始めましょう。
ママの顔や声も、赤ちゃんにとっては最高の動機づけになります。
実践レポート|6ヶ月の赤ちゃん、寝返り成功までのプロセス
今回の赤ちゃんは、仰向けでは活発に手足を動かし笑顔も多め。
ただ、うつ伏せになるとすぐに反ってしまい、手が開かずに泣き出してしまう様子が見られました。
また、向き癖の影響か、首の回し方や視線の動きにも左右差がありました。
まずは首・肩・背中の力を抜く関わり方からスタート。
姿勢の癖に応じたふれ方や、日常生活での「ちょっとした角度の工夫」も意識しました。
マッサージで筋肉を緩め、赤ちゃんのペースで遊びながら少しずつ左右差にアプローチしていきました。
なんとレッスン中に、ママの声かけとサポートで寝返りに成功!
その後も寝返り返りができるようになり、動きに迷いがなくなっていく姿が見られました。
「これまで動かなかったのは、やりたくないからじゃなくて、“どう動けばいいかわからなかっただけ”なんだ」
ママのこの言葉が、とても印象的でした。
ママの安心が、赤ちゃんの安心に繋がる
赤ちゃんが反るのは、嫌だからではなく「伝えたい」から。
今の気持ちや身体の状態を感じ取り、ママが受け止められるようになると、赤ちゃんも安心して表現できるようになります。
がんばって教えるのではなく、「その子が動きたくなる場面をつくる」ことで、発達はぐんと進みます。
動かしやすい身体の土台として、「身体の3Dでの感覚」「しなやかな筋肉のためのマッサージ」は欠かせません。その後、「親子で楽しくできる遊び」「日常姿勢の意識」により、わが子に合ったサポートになっていきます。わが子に合ったアプローチを見つけていきましょう。